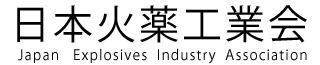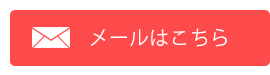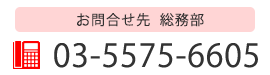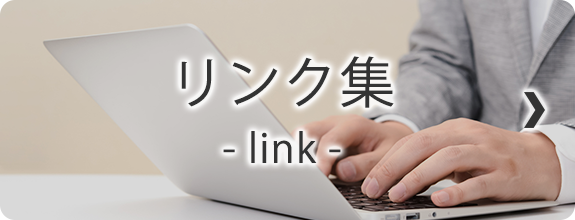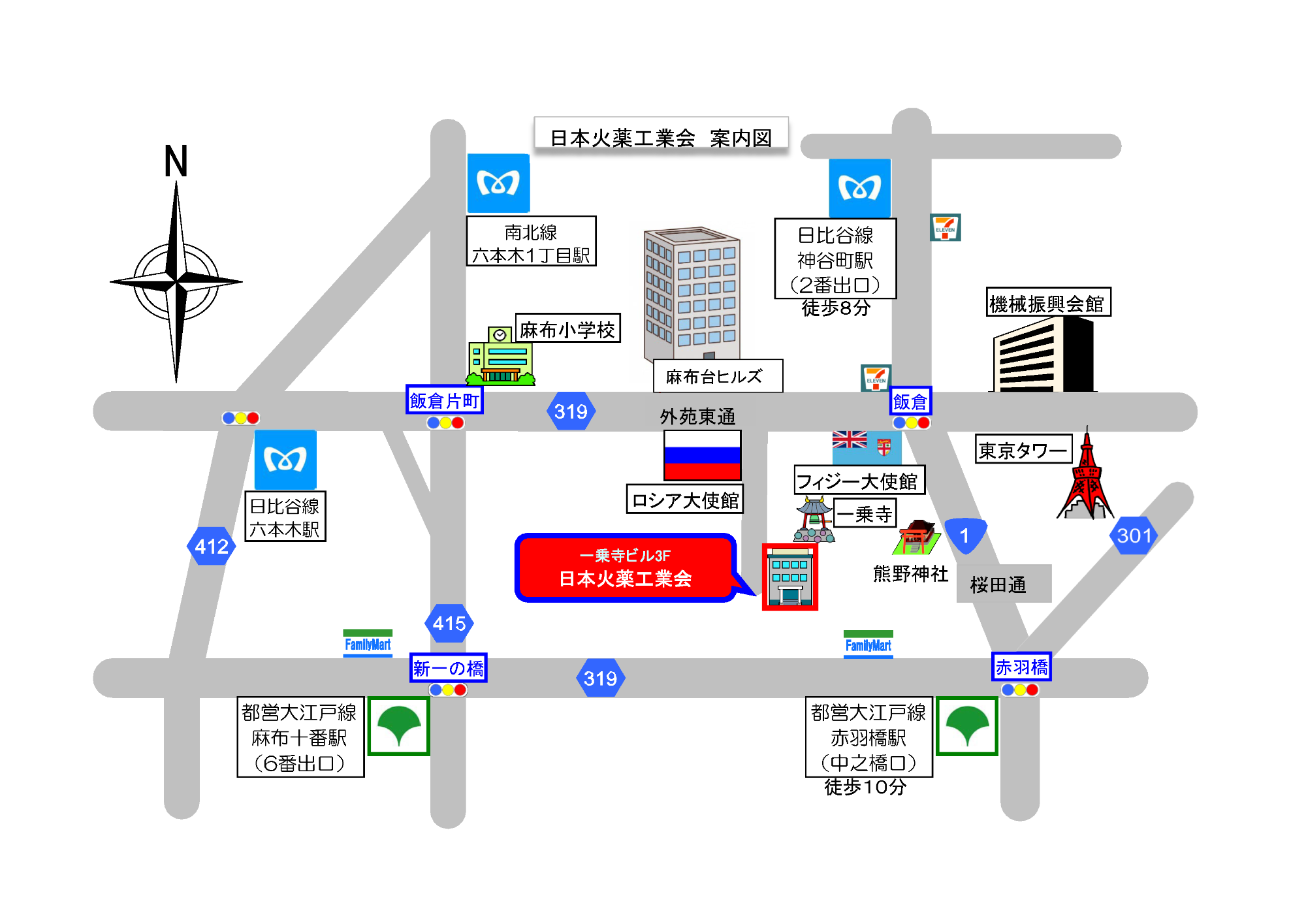工業会のご紹介
日本火薬工業会 会長 挨拶

令和8年1月7日
令和8年 賀詞交歓会 会長挨拶
日本火薬工業会
会長 豊田 憲太郎
新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、清々しい気持ちで新年を迎えられたことと心よりお慶び申し上げます。
ただいまご紹介いただきました、日本火薬工業会 会長の豊田でございます。年頭にあたり謹んでご挨拶を申し上げます。
本日は年初のお忙しい中、120名を超える皆様にお集りいただき、誠にありがとうございます。ご来賓として、経済産業省から産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官 佐藤様、製造産業局 素材産業課 菊池様をはじめ各課員の皆様、さらには学術界・関係団体からも多数ご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。また、平素より当会の活動へのご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
令和7年の産業用爆薬の需要は、リニア中央新幹線工事の進展があったものの、大型工事の終了や北海道新幹線関連工事のピークアウトにより、全体として厳しい状況が続きました。爆薬の出荷量は前年比96.5%の約26,700トン、電気雷管は前年比91.4%の約572万個と、依然として低調です。
令和8年の見込みも、爆薬は前年比97.7%で約600トン減の約26,100トン、電気雷管は前年比97.4%で約15万個減の約557万個と大きな回復は見込みにくい状況ですが、今年10月発表の建設経済研究所の見通しによれば、政府・民間ともに建設投資は継続して増加との発表があり、1~2年後には明るい兆しが見えてくるものと期待しております。
産業火薬業会は減災・防災や国土強靭化を始めとする社会基盤整備や経済安全保障において不可欠な存在であり、今後も安全管理の徹底と技術の高度化を通じて社会に貢献し続ける所存です。一方で、需要減が長期化する場合、当会会員各社の経営努力にも限界がありますので、政策面でのご支援、業界の魅力発信、人材確保に向けた取り組みについて、皆様との意見交換を重ね、実現につなげていきたいと考えております。
次に、昨年の活動状況についてご報告させていただきます。一昨年の「火薬類製造所における保安指針」の改訂に続き、昨年は「火薬類製造所の保安管理技術」に関して、当会技術保安部会のメンバーを中心とする編さん委員会により、経済産業省 鉱山・火薬類監理官付の方々のご協力もいただきながら1月から改訂作業を進め、12月より改訂版の販売を開始いたしました。編集委員の皆様、経済産業省 鉱山・火薬類監理官付の皆様方には、長期にわたりご協力を賜りまして、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。この書籍が関係各所で活用され、火薬類保安の一助となることを願っております。
昨年はこれに並行し、「火薬類取締法令の解説(通称:赤本)」の改訂にも着手いたしました。こちらは8月から本日ご臨席の新井先生に編集委員長をお願いし、全国火薬類保安協会様、日本煙火協会様、日本火薬銃砲商組合連合会様よりご参加をいただき、経済産業省 鉱山・火薬類監理官付の方々にもアドバイスをいただきながら、前回改訂以降の法改正等の反映を中心に作業を進めました。まずはご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。編集作業は終盤にかかっており、あと少し時間を要しますが、発行時期が分かり次第HP等にてお知らせいたしまので、その際には是非ご購入をお願いいたします。
また、当会の今年の主な取り組みとしましては、例年通り関係団体からの情報収集に努め、的確に会員各社に共有するともに、部会活動、製造保安責任者研修会、労使保安懇談会等を開催し、火薬類の保安にかかわる技術情報・法改正情報等を周知してまいります。また、製造保安責任者の後継者育成に寄与するため、製造保安責任者試験の準備講座である「火薬類の製造と保安の講習会」も引き続き開催いたします。
以上ご紹介した活動を通じて、今後も保安技術の向上と人材育成に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
最後になりますが、皆様のご健勝、ご発展を心より祈念し、年頭のご挨拶といたします。
ありがとうございました。
以 上
昭和15年6月、当時の火薬製造会社13社は、共同出資して日本火薬工業組合を設立した。昭和16年、太平洋戦争に突入し戦時統制が更に進展するにつれ、日本の全産業は統制下に置かれた。終戦後、全産業の統制は解かれそれぞれの産業が独自に自由経済への道を模索し始めた。
戦時統制が強化されるにつれ、昭和17年4月、日本火薬共販株式会社と 日本火薬工業組合は合体して日本火薬統制株式会社を設立し、資材の確保、製品の販売の両面を取り扱うことになった。更に戦局が進展するにつれ、日本の全産業をより強力な統制下に置かなければならなくなり、化学工業関係全体の統制機関として化学工業統制会が出来、火薬工業はその第三部会火薬部に属し、そこで生産計画、資材の割当て及び製品の配給割当てを行うようになった。そして昭和19年3月、統制会社令に基づく統制会社となり、社長も化学工業統制会第三部長が兼務して終戦に至った。
日本火薬統制株式会社は昭和20年末GHQに対して、日本の産業火薬類生産再開に関する陳情書を提出する等終戦後の火薬業界のため極めて重要な活動をした。その後も火薬統制会社は業界を代表してGHQとの折衝に当たり、火薬類の生産割当て等の仕事をし、火薬産業が終戦後の混乱からいち早く立ち上がることが出来るよう努力した。
昭和21年9月、日本火薬統制株式会社は、他の統制会社と同様にGHQから解散を命ぜられたので、日本火薬販売株式会社を設立して販売面の仕事を、日本火薬工業組合を設立して資材の割当申請等をすることとなった。この頃は制度の変更が激しく、昭和22年3月、日本火薬販売株式会社は閉鎖機関となり、続いて火薬類は指定生産資材に指定されたので、日本火薬工業組合も昭和22年7月に解散して、火薬類の受給割当、資財の割当は商工省の化成課が行うことになった。しかし、仕事の実務面は、火薬製造会社が昭和22年4月に設立した火薬懇話会がこれに協力した。ところがこのような会が配給業務等に携わることは、独占禁止法上問題があるとのことで、昭和23年4月に火薬懇話会も自粛解散しなければならなくなったので、これに代わるものとして昭和23年5月火薬業界は事業者団体令に基づいて日本産業火薬会を設立した。
平成2年5月、日本に於ける火薬類に関する唯一の事業者団体であることを明確にする趣旨で「日本火薬工業会」と名称を変更した。
日本火薬工業会設立経過 →設立経過説明図
規約・目的・事業内容
【規約】
日本火薬工業会規約 →規約
【目的】
火薬工業の発達に必要な事項について調査研究し、業界の公正な意見を明らかにすると共に、会員相互の親睦、連絡及び啓発を図り、会員の事業に共通の利益を増進し、本工業の健全なる発展を計ることを目的とする。
【事業内容】
- 業界の公正な意見を取り纏め、必要に応じ政府又はその他の関係機関に意見を具申すること
- 会員相互の親睦及び連絡の緊密化を図り、情報の交換を行うこと
- 火薬類及びその原材料の品質の改善、規格の改良に努めるよう推進し、生産若しくは流通の能率の向上を図ること
- 火薬類の輸出の振興及び原材料の輸入の合理化を図るため、必要な調査並びに企画を行うこと
- 海外関係機関との連絡又は視察団の派遣等により、諸外国の火薬工業事情を調査研究すること
- 火薬類の保安に関する教育及び啓蒙に努め、保安思想の普及を図ること
- 統計その他関係資料を蒐集し、これを総括して会員に提供し、又は公刊すること
- 機関誌の発行並びに講演会、研究会及び懇談会の開催等を行うこと
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
日本火薬工業会機構図 →機構図
活動状況
日本火薬工業会 事業報告
・・・ (工事中)
日本火薬工業会 事業計画
略年表
日本火薬工業会略年表 →略年表 [昭和23年(1948年)~令和6年(2024年) 8月]
経済産業省(旧通商産業省)主催の火薬類保安技術実験年表→保安技術実験年表[昭和30年(1955年)~令和6年(2024年)]
春季火薬類製造保安責任者研修会見学会開催場所→見学会開催場所[平成13年(2001年~令和7年(2025年)]
火薬工業技術奨励会の発足から解散まで →資料